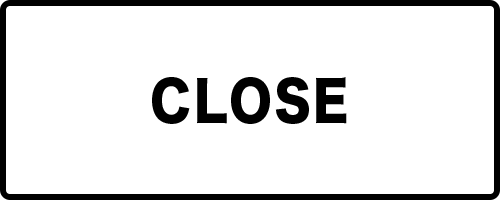PRODUCTION NOTES
プロダクションノート
- 原作の脚色と、テーマに対する様々な視点
-
小説“最期の教え”は、母娘の詩的な会話で構成されており、そのまま映画化すれば、母娘間で交わされる物事を映し出すだけのドキュメンタリー作品になってしまうことを懸念した監督は、まず自ら全体の流れを書き、それから脚本家のロラン・ドゥ・バルティーヤに加わってもらったと言う。「私は劇映画を作りたかった。目標や葛藤、対立する視点を描き出す映画を。だからロランと共に、ノエルや彼女の姉、そしてミレイユの存命の友人たちにも話を聞きながら、少しずつ中身の濃い脚本に作り変えていったの。この作業には長い熟考が必要で、結局執筆に2年以上の月日がかかったわ」
ノエルや彼女の兄弟姉妹は映画に実名で登場することを望まず、監督もノエルの兄(元フランス首相のリオネル・ジョスパン)を描くことが主題ではなかったので、彼らは原作に描かれた母と娘の関係を軸に、架空の家族を作り出した。
ノエルは言う。「映画に登場するのは、私の家族とは違う虚構の家族。映画化に際し、現実を脚色してフィクションにすることを受け入れなくてはいけなかったのは事実ね。母の決断に対して敵意をむき出しにする兄の存在も最初は受け入れがたいものだった。現実とはかけ離れていたから。でもパスカルが描きだした家族は、それぞれが母親の決断に異なる見解を示す。この問題に接する現実社会の有り様を映し出しているわ」
そしてノエルは続ける。「映画の完成時、私1人だけで試写を見せてもらったのだけど、その上映中に突然、まるで白昼夢のように、観客で劇場がいっぱいになるのを感じ、そして思ったの。“これが私の物語だということなど、どうでもいい。今では、みんなの物語になったのだ”って。私の心は少し締め付けられたけれど、同時にホッとしたのも本当よ。本の役割が、映画に受け継がれた瞬間だったわ」