
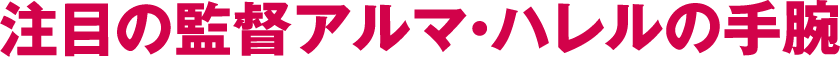
ラブーフが脚本について最初に連絡をしたのは、親友でありコラボレーターでもあるアルマ・ハレル監督だった。映画祭で常に話題となる独特な美学で知られる彼女は、最近ではポン・ジュノ監督から「2020年代に注目すべき気鋭監督20人」の1人として名前を挙げられている。ハレルはラブーフと初めて会った時の印象をこう語る。「初対面の夜から、本作について取り組み始めたようなものよ。私たちは夕食をとりながら、父親についてたくさん話したの。初めて会った時は、映画を作る話はしなかったけれど、すぐにあり得ないほどの親しみを感じ、お互いに共感し合ったわ」。ハレルが構想中に抱いていたイメージは、“オーティス=ピノキオ”だった。「ピノキオは他人に支配されている少年よ。操り人形のワイヤーを外して本物の少年になることだけを望んでいるのに、嘘をつき続け、それで鼻がどんどん伸びていくのが、みんなにも見える。ピノキオは『勇敢で、誠実で、自分勝手ではない』と証明した場合だけ、本物の少年になることができる。最後には、進んで父親を助けて、勇敢で誠実で自分勝手ではない行動で、本物の少年になれるの」。2人で作業を始めた時、ラブーフはまだリハビリ中だったので、ラブーフがハレルに草稿を送り、ハレルがコメントを書いたり指示を出したりしてラブーフに送り返すなどの作業を繰り返した。そのやり取りの中で、初稿にはなかった大人になったオーティスの描写を入れるようアドバイスした。感情的に混乱した幼少期を経て成人を迎える若者を見せれば、この映画に強力な文脈が生まれるという意図があったのだ。またラブーフがリハビリ治療を通して体験したことを入れ込むことも勧めた。この作業は結果的にラブーフのセラピーを促進させることなったのである。